06/17
Mon
2013
第9話
《 主 4、および吉康一 2 》

人が生きていくために必要なのは、必ずしも愛ではない。
どう生きるか。
何をするか。
拠りどころは?
これらの根幹を支える物語こそ、人には必要だ。
定められた運命や正義のようにして物語に従い、手を引かれるように
しながら生きてゆく。
しかし、それにしても。
この時代は物語を夢見ることさえ困難なのだ。めぼしい何かといえば、
「家族が一番」
「地域を愛する」
「実力行使で守る」
「破綻前に脱出せよ」
情熱は消えた。持て余す者は多い。
若い層のなかには、現状を諦観しつつ、ほぼ本能的に自らを器用に
コントロールしながら生き延びようとする人間もいる。
昨晩。
「食堂」の柱時計は2時前。
吉康一がやってきた。彼らしからぬ不作法をしてテーブルに腰かけると、
片膝を立て、闇のなかでじっと動かない。

彼の芯は、動揺と寂しさに悴んでいる。
自らの泉と名付ける事柄は、物語として脆弱なのを彼自身も承知しており、
そもそも物語はすでに放棄しているのだった。芯の内部で怒りが高まる。
15分ほどして出ていった。
ほどなく、ゴガ、というかすかな物音、少し間をおいて、ゴンという低い音。
闇のなかを、自らのコレクションであるステレオスピーカーを抱え、
吉が戻ってきた。

「食堂」の隅にスピーカーを置き、息を整えながら室内の壁面を見やる。
およその寸法を目測してから「食堂」を出ていくと、すぐさま紙の束を携え
戻ってきた。

ここで初めて蛍光灯をつけ、顔をしかめながらも動きは止めず、
住人たちが最も視線を向けるであろう壁の特等席に歩み寄ると
1枚のポスターを張り付けた。ひき伸ばされた、60年代と思しき
「LIFE」誌の表紙。ジャクリーン・ケネディがいた。
ゆっくりと後退しながら、ポスターの平行バランスを確認する瞬間、
ファーストレディーの微笑に誘惑されて彼の心身のテンションは忽ち高まった。
堰を切ったように行動を開始する。

腰の高さほどの棚から食器類を手際よく取り出し、軽くなったそれを室外へ。
代わりに、胡桃の木製の食器棚(1960年代後半の製造)、ステレオ本体、
残るもうひとつのスピーカーなど‟大物”たちを運んできた。
食器棚は、上段がガラス引き戸、下段の扉は観音開きになっている。
時間をかけて1点ずつ運んだ。
自らの体を衝撃吸収材のように使いコレクションを守りつつ、音を立てぬよう
神経を尖らせながら。
続いて彼は、室内をゆっくりと周回し、この空間の様相を決定づける核と
なろう‟大物”たちの配置について、思考を巡らせる。
作業により深く集中するにつれ、闇のなかで片膝を立てていた半時前の険は消え、
瞳に強さが宿ってゆく。決定した位置に1点ずつ運び、家具同士の間隔や向きを
微調整していく。
作業は加速する。キャラクターが描かれたスチール製看板(擬人化された
落花生が片眼鏡をかけポーズをとる)、傷みやすいボディを持った人形たち、
木の葉が描かれ、オレンジ色をした円形のサイドテーブル、「ゴッド・ファーザー」
「ピンクの豹」などのレコード数十枚を運び込む。レコードジャケットには、
the kinksなどの文字も見える。

品数がある程度揃うと、そのいくつかを手に取り、空間全体を俯瞰しながら
壁や棚に配してゆく。絵画の1点々々を展示室に設置する学芸員の静謐と
注意深さを失わない。並行して足りない素材はその都度、自室から調達してくる。
彼にしか聴こえないビートのなかで軽やかにダンスするような作業の反復。
素材を即興的に配置し、甘い少女趣味や外連味たっぷりのドールたちを
ちりばめてゆく。食器棚のガラス越しに、コレクションのコーヒーカップと
ソーサー、花柄のケーキ皿をディスプレイした。

突発的かつ個人的な“模様替え”前の「食堂」の名残といえば、もはや部屋
中央の大テーブルと10脚の椅子、備え付けの棚だけだ。棚のなかには彼の
コレクションが花の如く満開になった。
吉は、「食堂」の変身をついに遂行してしまった。

活躍の機会に恵まれなかった雑貨たちも、彼の丁寧な扱いで、元の部屋の
しかるべき保管場所へ帰っていった。ゴミを片付け最後の微調整を済ませると、
彼は部屋の片隅から自らの作業成果をゆっくりと見渡した。しばらくすると
床に腰を下ろし、胡坐をかいてさらに眺めた。わずかに上体を揺らし、空間に
酔いしれる。
その時。
怒りが瞬時に彼の芯を支配した。吉は立ち上がり、それまで数十回と
繰り返してきたようにいったん部屋を出るとすぐ戻ってきた。
人が生きていくために必要なのは、必ずしも愛ではない。
どう生きるか。
何をするか。
拠りどころは?
これらの根幹を支える物語こそ、人には必要だ。
定められた運命や正義のようにして物語に従い、手を引かれるように
しながら生きてゆく。
しかし、それにしても。
この時代は物語を夢見ることさえ困難なのだ。めぼしい何かといえば、
「家族が一番」
「地域を愛する」
「実力行使で守る」
「破綻前に脱出せよ」
情熱は消えた。持て余す者は多い。
若い層のなかには、現状を諦観しつつ、ほぼ本能的に自らを器用に
コントロールしながら生き延びようとする人間もいる。
昨晩。
「食堂」の柱時計は2時前。
吉康一がやってきた。彼らしからぬ不作法をしてテーブルに腰かけると、
片膝を立て、闇のなかでじっと動かない。
彼の芯は、動揺と寂しさに悴んでいる。
自らの泉と名付ける事柄は、物語として脆弱なのを彼自身も承知しており、
そもそも物語はすでに放棄しているのだった。芯の内部で怒りが高まる。
15分ほどして出ていった。
ほどなく、ゴガ、というかすかな物音、少し間をおいて、ゴンという低い音。
闇のなかを、自らのコレクションであるステレオスピーカーを抱え、
吉が戻ってきた。
「食堂」の隅にスピーカーを置き、息を整えながら室内の壁面を見やる。
およその寸法を目測してから「食堂」を出ていくと、すぐさま紙の束を携え
戻ってきた。
ここで初めて蛍光灯をつけ、顔をしかめながらも動きは止めず、
住人たちが最も視線を向けるであろう壁の特等席に歩み寄ると
1枚のポスターを張り付けた。ひき伸ばされた、60年代と思しき
「LIFE」誌の表紙。ジャクリーン・ケネディがいた。
ゆっくりと後退しながら、ポスターの平行バランスを確認する瞬間、
ファーストレディーの微笑に誘惑されて彼の心身のテンションは忽ち高まった。
堰を切ったように行動を開始する。
腰の高さほどの棚から食器類を手際よく取り出し、軽くなったそれを室外へ。
代わりに、胡桃の木製の食器棚(1960年代後半の製造)、ステレオ本体、
残るもうひとつのスピーカーなど‟大物”たちを運んできた。
食器棚は、上段がガラス引き戸、下段の扉は観音開きになっている。
時間をかけて1点ずつ運んだ。
自らの体を衝撃吸収材のように使いコレクションを守りつつ、音を立てぬよう
神経を尖らせながら。
続いて彼は、室内をゆっくりと周回し、この空間の様相を決定づける核と
なろう‟大物”たちの配置について、思考を巡らせる。
作業により深く集中するにつれ、闇のなかで片膝を立てていた半時前の険は消え、
瞳に強さが宿ってゆく。決定した位置に1点ずつ運び、家具同士の間隔や向きを
微調整していく。
作業は加速する。キャラクターが描かれたスチール製看板(擬人化された
落花生が片眼鏡をかけポーズをとる)、傷みやすいボディを持った人形たち、
木の葉が描かれ、オレンジ色をした円形のサイドテーブル、「ゴッド・ファーザー」
「ピンクの豹」などのレコード数十枚を運び込む。レコードジャケットには、
the kinksなどの文字も見える。
品数がある程度揃うと、そのいくつかを手に取り、空間全体を俯瞰しながら
壁や棚に配してゆく。絵画の1点々々を展示室に設置する学芸員の静謐と
注意深さを失わない。並行して足りない素材はその都度、自室から調達してくる。
彼にしか聴こえないビートのなかで軽やかにダンスするような作業の反復。
素材を即興的に配置し、甘い少女趣味や外連味たっぷりのドールたちを
ちりばめてゆく。食器棚のガラス越しに、コレクションのコーヒーカップと
ソーサー、花柄のケーキ皿をディスプレイした。
突発的かつ個人的な“模様替え”前の「食堂」の名残といえば、もはや部屋
中央の大テーブルと10脚の椅子、備え付けの棚だけだ。棚のなかには彼の
コレクションが花の如く満開になった。
吉は、「食堂」の変身をついに遂行してしまった。
活躍の機会に恵まれなかった雑貨たちも、彼の丁寧な扱いで、元の部屋の
しかるべき保管場所へ帰っていった。ゴミを片付け最後の微調整を済ませると、
彼は部屋の片隅から自らの作業成果をゆっくりと見渡した。しばらくすると
床に腰を下ろし、胡坐をかいてさらに眺めた。わずかに上体を揺らし、空間に
酔いしれる。
その時。
怒りが瞬時に彼の芯を支配した。吉は立ち上がり、それまで数十回と
繰り返してきたようにいったん部屋を出るとすぐ戻ってきた。
足取りは一変し、ほかの住人の眠りなどおかまいなしだ。
右手には、WELEDAのサルビア。
「食堂」じゅうにスプレーを吹きつける。躊躇も容赦もない。
「食堂」じゅうにスプレーを吹きつける。躊躇も容赦もない。
瞬きひとつせず、隅々までぶちまける。同じ箇所にもお構いなしに、
烈しく、執拗にまき散らす。
身体は、先ほどの軽やかさを永遠に失い、律動を放棄した。
突然、止まる。肩で大きく息をしている。
ドスン、と膝をつき、その場にうずくまってしまった。髪や肩、顔を覆う
指先を小刻みに震わせている。時折、眼鏡の縁や頬から涙がこぼれ落ちる。

私はここに暮らすどの住人にも干渉すまい。だが、眼下の男の姿は愚かしく
憐れで、その孤独のため殊更にかわいい。
ガザ、とふいに、玄関から新聞紙の落下音がした。
この朝一番に急き立てられて、彼は、這うようにした後、ゆっくり立ち上がり、
明かりを消して去っていった。
柱時計は5時を回っていた。
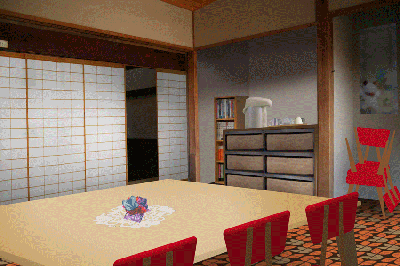
身体は、先ほどの軽やかさを永遠に失い、律動を放棄した。
突然、止まる。肩で大きく息をしている。
ドスン、と膝をつき、その場にうずくまってしまった。髪や肩、顔を覆う
指先を小刻みに震わせている。時折、眼鏡の縁や頬から涙がこぼれ落ちる。
私はここに暮らすどの住人にも干渉すまい。だが、眼下の男の姿は愚かしく
憐れで、その孤独のため殊更にかわいい。
ガザ、とふいに、玄関から新聞紙の落下音がした。
この朝一番に急き立てられて、彼は、這うようにした後、ゆっくり立ち上がり、
明かりを消して去っていった。
柱時計は5時を回っていた。
PR
Comment
プロフィール
HN:
甘地トシ子
年齢:
72
性別:
女性
誕生日:
1953/03/21
制作・提供
制作/
 提供/
サンダース・ペリー MIKI
TEL. 025-522-6006
FAX. 025-522-6042
新潟県上越市稲田2-6-10
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
ブログに関してのお問い合せはこちら gggggangi@Yahoo.co.jp
提供/
サンダース・ペリー MIKI
TEL. 025-522-6006
FAX. 025-522-6042
新潟県上越市稲田2-6-10
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
ブログに関してのお問い合せはこちら gggggangi@Yahoo.co.jp
ブログ内検索
ブログをご覧の皆様へ
物語に登場する人物名は、すべて創作上の架空の人物であり、実在するものではありません。
※画像内の商品撮影協力:ヴィンテージ&アンティーク雑貨のお店「ペチカ 」

